くまがい もりかず
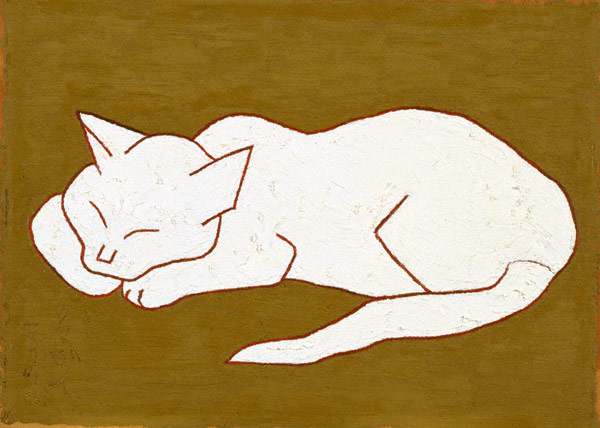
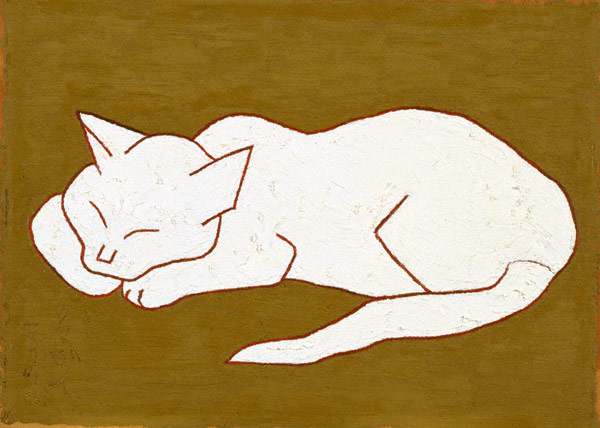


略歴
1880年4月2日 - 1977年8月1日(享年:97歳)
1880年 岐阜県恵那郡付知村(現中津川市付知町)に生まれる。
1900年 東京美術学校(現東京芸術大学)西洋画科に入学。同級生に青木繁がいた
1909年 第3回文部省美術展覧会に《蝋燭》を出品、褒状を受ける。
1910年 実母の死を機に故郷に帰る。
1916年 再び上京して第3回二科会展に出品、二科会会員に推挙される。
1932年 豊島区長崎町(現千早)に移り住み、生涯にわたりここで生活する。
1967年 文化勲章を辞退する。
1977年 8月1日に死去 享年97歳。
熊谷守一(くまがい もりかず)岐阜県恵那郡に生まれる洋画家。世俗から離れ、自由に制作を楽しみながら、単純明快なカタチと色で独自の様式を確立した。
熊谷守一は若い時から図抜けて素質のある画家だという評判が、仲間の間に高かった。 明治三十三年、二十歳で東京美術学校の油絵科に入った時、同級生に青木繁とか和田二一造とか山下新太郎とか、後年名を成した錚々たる画家たちがいたが、その連中が熊谷守一の画才にひとしく奇異の眼を見はっていたということだ。山下新太郎とは特に親しかったらしく、後になって山下新太郎は美術雑誌にこんなことを書いている。
―― 熊谷守一には当時からそれまで誰もやっていない絵を研究しているようなところがあって、モデルを見ながら丸だの三角だのを描いたり消したりしているのを不審に思って見ていたが、それからしばらく経った後で、フランスに立体派という新しい画風がおこつたことを知って、なるほどと篤いたものだった、などと述べている。明治三十三年といえば一九〇〇年で、フランスで立体派の運動が興る以前だから、山下新太郎の述べていることには、 多少買いかぶりもあるようだが、それにしても熊谷守一には前人未踏の絵の仕事をやりそうな気配を若い時から周りの者に感じさせるところがあったらしい。当時の先生はフランスから帰国して間もない黒田清輝だった。生徒の青木繁だの熊谷守一だのは、その黒田先生の絵に格別心服していなかったようで、青木繁などは明らさまに反抗の姿勢を示しているのだった。
「自画像」は熊谷守一の卒業制作だが、こういう赤褐色の一色を基調にした作品や、 同じ年に描いた「半裸婦』という絵など、黒田清輝の印象派的な作風とは全く違ったもので、当時としては全く異端のものだったのである。この頃の青木繁の自画像にも、熊谷守一 と同じょうな赤褐色一色を基調として描いたものがある。
それら初期作品の中でも、学校を出てから描いた「ローソク」とい絵は文展で受賞した作品で、この画家の初期の傑作として名高い。この時期、熊谷守一はレンブラントに傾倒していたようである。
熊谷守一は岐阜県の付知村の生まれで、父親は紡績工場を大きく営んでいて、貴族院議員などもやっていた家庭だったから、いわゆる素封家の息子である。子供の時から、父親のお妻さんが大勢一緒に住んでいるような家庭で育っているせいか、子供の時から大人はうさん臭いものだ、という不信の念を持っていたようである。その反動のように、子供や動物には無類の親しい愛情を本能的に持っていた。この子供や動物に対する無類の愛情は、その後も生涯を通じて熊谷守一は持ち続けた。
東京にいる画家の友達仲間にもそういう熊谷守 の消息は何と うこともなく伝わって、彼の画才を惜しんで上京を促す画家仲間が多くなった。彼は再び東京に戻っ て画家としての生活に入る。しかし、郷家からの経済的援助のないこの画家の生活は窮乏を極めるが、当時の油絵画家の生活というものは、一部の大家を除いては大同小異、皆貧乏は普通のことだったから、とくに熊谷守一はそういうことでは鍛え抜かれた人だったから、極貧の中でも彼は音楽をやる友達と親しくなったりして悠遊と過ごす。久しぶりに、『赤城の雪』を二科展に出品して二科の会員にも押されている。守一は三十六歳になっていた。それから引き続いて二科の会員として、そこに出品することになる。そのころの作品は比較的少ないが、『松』や『ハルシャ菊と百合』など、小品ながらなかなかの佳品である。四十二歳の時、和歌山県の素封家の娘大江秀子と結婚する。この夫人が、その後この画家が亡くなるまで、明治の人としては珍しいほど睦まじく生涯を共にした夫人である。
次々に子供が生まれる。長男が黄、次男が陽、次が長女の萬、次女榧、三女茜。次男陽が昭和三年に数え年四歳で亡くなった。子供好きのこの画家の悲歌は見るも無残であった。この頃、熊谷家は貧窮のどん底にあって、子供が病気でも医者にかけることも出来ない。 夫人は画家に絵さえ描いてくれたら、それを金に換えて医者をよぶことが出来るからと頼むのだけれど、画家はただオロオロするばかりで絵など描けない。後になって画家はこんな風に述懐する。「子供が病気で心配な時、絵を描けるような画家の気持ちが私にはわからない」。陽は死ぬ。画家はその枕元で亡くなったばかりの愛児の死顔を速写する。それが「陽の死んだ日」という中期の傑作でいま倉敷の大原美術館に蒐蔵されている。画家はこの絵を描いた後、死んだ愛児の枕元で絵を描いている自分を顧みて愕然とした思いをする。
この時期の作品は大まかな筆触で、色調は以前より明るくなり、どちらかというとフォープ的な作風が続く。昭和十年代で、この画家の五十代の時期である。「富士」、「鳥」、「桃」、「鉢山」など、いずれも小品で無造作そうに描いているが、珠玉の作品といっても過言ではないだろう。この頃、二科展の審査会場に、熊谷守一が自作の小品の出品画をぶら下げて現れると、当時健在であった小出楢重が、それを「天狗さまの小判」といって珍重したという話は有名である。
昭和二十二年、戦後間もなくの時期に画家は長女萬を亡くした。「ヤキバノカエリ」というこの画家のものとしては比較的大きな十二号の絵は、この時のかたみの作品である。この時、 画家は六十七歳であった。あごの髭もすでに白かった。
このころから熊谷守一の画風は晩年に続く様式として、だいたい定まってきたようである。もちろん少しずつの推移、進展はみられるが、そう大きな作風の変化はない。晩期の画風は一口に言えば簡朴の一語に尽きるかもしれない。その簡朴な様式のうちに無限の滋味を堪えているものと言えるだろう。
晩期の作品中には、われわれはあれが好き、これが好きというようなことは言えるかもしれないが、どの作品もほとんど出来、不出来を示さない同じような力の充実した絵で、その点が熊谷守一という画家の作品の一つの特徴でもある。この画家の自伝が昭和四十年、九十一歳の時に『へたも絵のうち』という題で綴られ、日本経済新聞社から発刊された。その中で、この画家は語っている。「私は子供の時から他人を押しのけて前に出ようとする気がないから、何も怖いものはないのです」といっているまた、先年亡くなった画家坂本繁二郎のことにふれ、「あの人は金欲も名誉欲もない人だったようですが、ただいい絵を描こうという気持だけは強かったようだ。私には特にいい絵を描こうという気ないのだから不心得者なのです」と語っている。
生涯を通じてこの画家ぐらい、鳥や虫や草や花に深い気持ち通わせた画家はほかにはいないであろう。晩期の作品がそのことを明らか語っている。
大切な財産だからこそじっくりと丁寧にご相談内容をお聞きします。